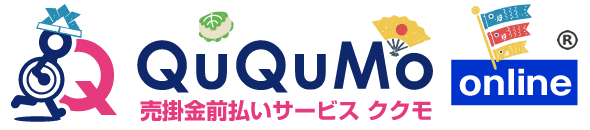2025-10-28
🔍支払督促について詳しく知っておこう

支払督促についてご存知ですか。
聞いたことはあるけれど、詳しく知らないという方も多いかもしれません。
支払督促とはどんなものなのか、支払督促をする場合をはじめ、支払督促を受けるとどうなるのかについて詳しく見ていきましょう。
■支払督促とは

支払督促とは、支払いを求める方は簡易裁判所に申し立てることで、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
訴訟を起こす場合に比べて簡易な手続きで、裁判所の強制力を持った督促を可能とします。
手続きの対象とできるのは、金銭の支払いか、有価証券もしくはその代替物の引き渡しを求める場合に限られます。
手続きは、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることが必要です。
書類審査のみで完結できるので、支払いを求めて訴訟を起こすのとは異なり、審理のために裁判所に行く必要もありません。
支払督促の手続きに支払う手数料も、訴訟に比べて半額で済むので低コストです。
なお、相手方である債務者が支払督促に対して異議を申し立てると、請求額に応じて簡易裁判所または地方裁判所における民事訴訟の手続きに移行します。
債務者が異議を申し立てなければ、申立人は仮執行宣言を申し立てることができます。
債務者は仮執行宣言付支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所へ異議を申し立てることも可能です。
債務者が異議を申し立てると、その場合も訴訟へ移行することになります。
これに対して、債務者から異議の申立てがなければ、申立人の請求が認められ、強制執行が可能となります。
■支払督促が行われるケース
では、支払督促はどのような場合に行われる手続きなのでしょうか。
たとえば、お金を貸したところ、約束した返済日を過ぎてもなかなか返してもらえないケースや商品を売掛取引で販売したところ支払期日が来ても支払ってもらえず、代金を回収した場合などに支払督促をすることが可能です。
また、滞納されている家賃を請求することや従業員が会社に対して支払いが滞っている給料や残業代などの支払いを求めることもできます。
ビジネスシーンをはじめ、日常生活において発生する金銭の未払いに関するトラブルに使える制度です。
■支払督促を利用するメリット
金銭トラブルが生じて貸したお金を返してほしい場合や商品代金を払ってほしい場合、滞納している家賃や給料の支払いを求めたい場合、民事訴訟を提起して請求することも可能です。
もっとも、訴訟を起こすには手間もかかり、弁護士に依頼するなど高額な費用も発生します。
経済的にも精神的にも負担が大きく、時間もかかるのが難点です。
そのため、裁判に訴えることなく、いつまでも相手とトラブルを抱え続け、解決できずにいる方は少なくありません。
いつまでも支払ってもらえるのを待つという無駄な時間を過ごすだけでなく、時間が経過することで相手が自己破産してしまう場合やお金がなくなり支払ってもらえなくなるリスクもあります。
そうした場合に、支払督促を利用すれば、裁判に訴えるより低コストで、より簡単な手続きでスピーディーに支払いを求め、金銭トラブルの解決が可能となります。
■支払督促の概要

支払督促は、裁判で裁判官が判決を下すのとは異なり、簡易裁判所という、最も身近で簡易的な手続きを行っている裁判所の書記官が、書面上で申立内容を審査し、債務者に対して金銭の支払いを督促してくれる略式の手続きです。
申立人からの申立書を審査した後、書記官が支払督促を発付し、債務者へと送付されます。
債務者は支払督促に対し異議があれば、支払督促を受け取った日から2週間以内に裁判所へ異議を申し立てることが可能です。
異議を申し立てた場合は、訴訟へ移行することになります。
債務者が異議を申し立てなければ、申立人は仮執行宣言を申し立て、債務者から異議申立てがなければ、債務者の財産に対して強制執行を行うことができます。
■支払督促の対象にできるもの
支払督促は、金額の大小は問わず、次のような金銭の未払い、未返還などを対象にできます。
貸し付けたお金の未返済や代わりに立て替えた立替金の未払い、売買代金の未払い、給料や報酬の未払い、請負代金や修理代金の未払い、家賃や地代の未払い、契約期間が終わったら貸主が借主に返すべき敷金や保証金が未返還の場合などです。
■支払督促の特徴やメリット
支払督促を行うにあたっては、裁判所に出向く必要がありません。
なぜなら、書類審査のみで行われる手続きでだからです。
そのため、訴訟のように裁判所に出向くことや証拠を提出する必要がないので、簡単で精神的にも楽です。
証拠集めをする必要も手間もかかりません。
また、裁判所に納める手数料が、訴訟の場合の半額で済みます。
たとえば、100万円の支払いを求める場合、訴訟の場合は裁判所に納める手数料は10,000円必要になりますが、支払督促は半額なので5,000円で済みます。
支払督促をしても、相手方が支払いを行わず、異議申立てもしない場合には、申立人は仮執行宣言を発付してもらうことができ、最終的には強制執行を申し立てることが可能です。
支払おうとしない相手に対して、その財産に強制的に執行をかけてもらえるので、なんらかの財産があれば、金銭の回収が確実にできるのがメリットです。
■支払督促の注意点
支払督促を受けた相手方は、身に覚えがない場合や納得できない場合には異議申立てをすることができます。
逆に言えば、支払督促がスムーズに行くケースは、金銭の支払いや支払額や支払時期、契約の有無などについて相手方が納得しているケースです。
たとえば、商品を販売して代金をいつまでに支払ってもらう約束をしているのに支払ってくれない場合に、相手方が確かに約束をしているが、お金が用意できず、支払えていないと認めている場合などです。
これに対して、そんな約束はしていない、金額が間違っている、支払日は定めていないなど、なんらかの反論をしてきた場合は訴訟に移行することになります。
そのため、相手方が納得していないような場合や異議申立てをするおそれがある場合には、支払督促ではなく、最初から民事調停や民事訴訟を行ったほうがスムーズな場合もあります。
また、支払督促は書類を郵送して行われる簡易な手続きです。
そのため、相手方の住所がわからないと支払督促ができないので注意しましょう。
お金を貸した相手が行方をくらますなど、どこにいるのかわからず、住所がわからない場合には支払督促はできません。
■支払督促の手続きの流れ
支払督促の手続きは、2段構えになっています。
支払督促を行い、相手方から異議申立てが出ると訴訟に移行してしまい、異議申立てがなければ仮執行宣言付の支払督促へとつなげることができます。
支払督促をしたい場合には、申立人は支払督促申立書を入手し、必要事項を記入して、相手方の住所地の簡易裁判所に提出することが必要です。
支払督促の申立書は簡易裁判所に備え付けてありますが、裁判所ホームページからダウンロードできるので、簡易裁判所に出向く必要なく入手が可能です。
申立書に必要事項を記入したうえで、裁判所に支払う手数料と相手方に書類を送るための郵便切手などを添えて、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に直接提出しに行くか、郵送することもできます。
なお、申立人が法人の場合には、法人の登記事項証明書1通の添付も必要です。
申立書が届くと、簡易裁判所の書記官が内容を審査し、申立ての主張から請求に理由があると認めれば、支払督促を発付し、相手方へと送達します。
一方、申立人には簡易裁判所より支払督促を発付したことを通知する文書が送付され、手続きが始まったことがわかるので、とりあえず安心です。
相手方が異議申立てをせず、かつ支払いが行われればトラブルは解決するので、支払督促手続きもその段階で終了します。
これに対して、相手方が支払督促の受領後、2週間以内に異議申立てをせず、かつ支払いが行われない場合には、申立人は簡易裁判所に対して仮執行宣言申立書を提出することが可能です。
異議申立てがなければ、自動的に仮執行手続きに移行するわけではなく、あくまでも申立人のアクションが必要となります。
仮執行宣言を申立てとは、金銭の回収手段となる強制執行を申し立てるために必要となる手続きです。
仮執行宣言の申立ては、相手方が支払督促を受領した後2週間を経過した日から30日以内に申し立てなければならず、期限を過ぎると支払督促が失効してしまい、一からやり直しになるので注意しましょう。
これに対して、相手方が簡易裁判所に異議を申し立て、異議申立てが受理された場合には、支払督促は失効し、民事訴訟の手続きに移行してしまいます。
民事訴訟は、紛争の対象となる金額が140万円以下なら簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所で行われることとなります。
■仮執行宣言を申し立てた場合
相手方が異議を申し立てないものの、まだ支払ってもらえない場合には簡易裁判所に対して仮執行宣言の申立てを行うことができます。
裁判所書記官は仮執行宣言の申立ての内容を審査し、問題がなければ、仮執行宣言を発付し、仮執行宣言付支払督促を相手方に送達し、申立人に対しても仮執行宣言付支払督促を送達します。
仮執行宣言付支払督促を受領した相手方は、受領後2週間以内に異議申立てをすることが可能です。
相手方が異議を申し立てると、やはり民事訴訟に移行してしまいます。
仮執行宣言付支払督促の送達後、異議申立てがなく、かつ相手方からの支払いがない場合には、申立人は簡易裁判所に対して差押えなどの強制執行の申立てが可能となります。
■支払督促を受けた場合の対応
ここまでは、支払督促を申し立てる側の流れなどをご紹介してきましたが、逆に支払督促を受けた場合、どう対応すれば良いのでしょうか。
支払督促は、特別送達という特別な郵便で送付されてきます。
郵便職員から名宛人に直接手渡されるのが基本です。
簡易裁判所から支払督促が届いたら、すぐに内容を確認しましょう。
請求の趣旨の欄に請求金額が記載されており、申立人の請求内容が請求の原因の欄に記載されています。
この内容に不服があれば、異議を申し立てることができます。
そもそも支払う約束をしていないといった場合や請求された金額に納得できない場合など、異議があれば、受領後2週間以内の制限があるので、速やかに異議申立てを行うことが必要です。
支払督促の書類と一緒に、異議申立書をはじめ、異議申立て方法の案内書面なども同封されています。
異議申立てをしたい場合には、異議申立書に必要事項を記入し、支払督促の送付元である簡易裁判所に直接持参して提出するか、郵送しましょう。
異議申立てをせず、2週間を経過してしまうと、支払督促の手続きが進み、最悪の場合強制執行を受けるおそれがあります。
一方、異議申立てが受理されると、民事訴訟に移行する点も覚悟しておきましょう。
■仮執行宣言付支払督促を受けた場合の対応
支払督促が届いても異議申立てをせず、かつ支払いもしないでいると、申立人が仮執行宣言の申し立てを行うことがあります。
支払督促に仮執行宣言が付されると、申立人は直ちに強制執行手続きを採れるようになります。
仮執行宣言付支払督促が送達された場合、その段階でも異議を申し立てることが可能です。
異議申立てをしたい場合、仮執行宣言付支払督促を受領した日の翌日から数えて2週間以内に行わなくてはなりません。
同封されている異議申立書に必要事項を記載し、簡易裁判所に直接持参するか、郵送しましょう。
ただし、異議を申し立てても、執行停止の手続きを採らないと、強制執行を止めることができません。
異議を申し立てると民事訴訟に移行しますが、異議申立てをしない場合には仮執行宣言付支払督促の内容について今後一切争えなくなるので注意しましょう。
■心当たりがない場合

近年、支払督促の手続きを悪用して架空請求を行う詐欺事例が増えています。
架空請求であったとしても、正規の手続きを踏んで出された支払督促であれば、定められた期間内に異議申立てをしないと、強制執行を受けてしまうおそれがあります。
まったく身に覚えがない支払督促を受けた場合は、自分には関係ないと無視するのではなく、速やかに簡易裁判所に異議申立てをするようにしましょう。
最近では、裁判所を騙って支払督促を装った書類が送り付けられる詐欺事例もあります。
驚いて指定された口座に振り込んだり、受け子に支払ったりせず、封筒や書類に記載されている裁判所の電話番号や住所などが実際に存在するのか、裁判所ホームページで必ず確認してください。
■まとめ
支払督促は、金銭の支払いや返還が行われない場合に、簡易裁判所を通じて簡単な手続きで督促できる手続きです。
相手方が異議申立てを行わず、かつ支払いをしない場合には強制執行を申し立て、未払金や未返還金の回収をすることができます。